





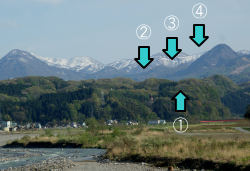









地蔵峠北側は巨木を貫く古道











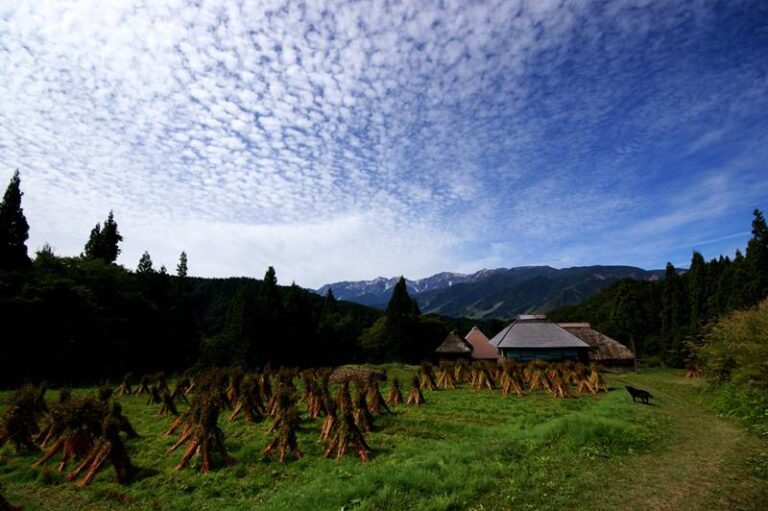


















佐野峠 西国三十三観音
初冬などの積雪時には旅人の道しるべともなっていた
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |



塩は、糸魚川から大町まで通常6日かけて運ばれた。最速の歩荷(一日追い)では、生魚・塩魚を運んだが、糸魚川を午後4時に出て翌夕方に大町に着いた。松本へは翌々朝に運ばれていた。





国の重要文化財






拾ヶ堰(じっかせぎ)文化13年の完成。水利権の関係で、梓川からは、取水ができず、奈良井川より取水し、梓川の地下をサイフォン原理にて水を通している。また、拾ヶ堰は、全長約15㎞、勾配5㎝/1㎞というわずかな勾配の土木技術で完成させている。江戸時代の技術力に驚きを感じる。現在の梓川の地下を通すサイホンは、平成10年に改修した。
塩の道からの雪形
雪形は、その年の気候にあわせた、農作業のタイミングの目安とされていました。感がたよりであった昔と同じ風景=雪形が、見れます。古を感じながら、雪形ウォッチングしませんか。5月連休から6月初旬が見ごろです。
青色の雪形 雪が無い部分の像形が雪形として見える
赤色の雪形 雪の部分の像形が雪形として見える。


松本から糸魚川へ
北アルプス 蝶が岳
アゲハ蝶
安曇野より
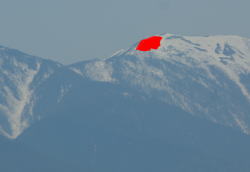

北アルプス 大天井岳
子犬
安曇橋より
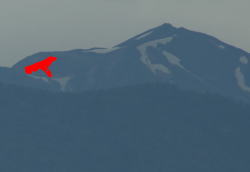

北アルプス 常念岳
常念坊
安曇野より


北アルプス 常念岳
万能鍬
安曇野より


北アルプス 爺が岳
左 南の種まき爺さん
右 北の種まき爺さん
大町より


北アルプス 鹿島槍ヶ岳
左 鶴
右 獅子 駆け下っている勇壮な姿
大町より


北アルプス 五竜岳
武田菱 塩の道が「もうひとつの風林火山」とも云われますが?
白馬より


北アルプス 八方尾根
上 猫 オリジナル
右 内裏様 オリジナル
下 手斧打ち(ちょうなうち)


北アルプス 小蓮華岳
左 種まき爺さん
右 種まき婆さん
栂池高原より


雨飾山
鶴と小鶴
親鶴の背中に子鶴(あひる?)が 親鶴の首が切れると田植えです


頚城山塊 駒ケ岳
ねこまんま
大久保集落より


黒姫山
上 舟窪
下 土瓶
大野より





